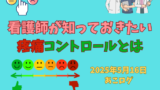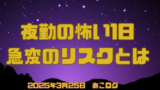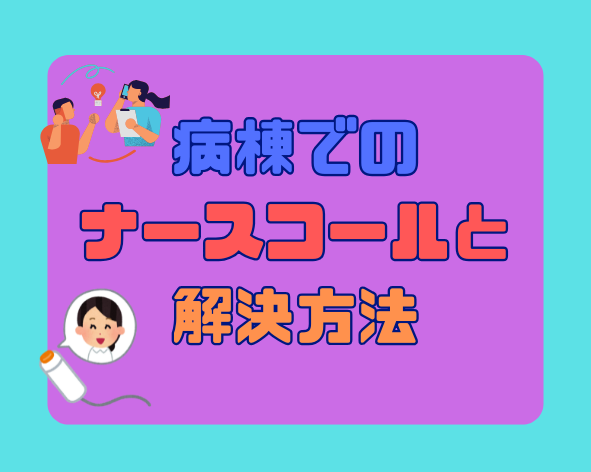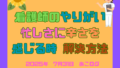ナース指導者が教える病棟でよくあるナースコール内容TOP7と解決方法
今回は私が現在でも経験している病棟でよくあるナースコール内容をそれをどのように解決したかについてお伝えしたいと思います。
病棟でのナースコール内容
患者さんがナースコールは押さずにセンサーマットやセンサーベッドで対応している場合もあります。それも含めてのナースコール内容としてます。
- トイレに行きたい
- 痛みがある(疾患によるもの)
- オムツを変えてほしい
- 家に帰りたい
- 用事はなくて押してみた
- お茶飲ませて
- 体の向きを変えて欲しい
ナースコール内容と解決方法
トイレに行きたい
手術後トイレへ行くのに制限がかかっていることがあります。その際にナースコールがあり看護師付き添いで車椅子を使用しトイレへ行くことがあります。またリハビリで歩行できるようになると歩行器でトイレへ行くことができるためこれも転倒予防で夜間は付き添って行くこともありますし、歩行器フリーの場合は自己で行かれることもあります。
痛みがある(疾患による)
痛みは手術後や原疾患による疼痛など様々あります。痛み止めは病棟で準備されていることが多く、痛み時は看護師に伝えるためにナースコールを押して知らせます。内服できる際はロキソプロフェンなどを使用しますが、できないときはボルタレン坐薬など非ステロイド性消炎鎮痛薬、オピオイド系鎮痛薬、神経障害性疼痛治療薬などが使用されます。点滴での痛み止めを使用する際は硬膜外鎮痛やPCA(患者管理鎮痛法)など持続的な皮下注射での投与を行う場合もあります。硬膜外鎮痛は硬膜外腔にカテーテルを留置し、局所麻酔薬やオピオイド鎮痛薬を継続的に注入する方法でPCAは患者が自分でボタンを押して鎮痛薬を投与できるシステムで主にオピオイド系の鎮痛薬が使用されます。オピオイド系鎮痛薬とはモルヒネ、フェンタニルなど強力な鎮痛薬効果を持つ薬です。神経障害性疼痛治療薬とはリリカ、タリージェなど神経の損傷により痛みを軽減する薬です。
オムツを変えてほしい
手術で一時的にオムツにしている場合に汚染により交換希望される場合があります。その際はすぐ交換し夜間では入眠を促します。フォーリーカテーテルを使用していることもあるのでその際は入眠を行うこともしやすいと思われます。
家に帰りたい
家に帰りたいと訴えることは認知症があり入院した理由を理解されていない場合に多くあります。今は超高齢社会となっており入院される患者さんは認知症がある方がほとんどと言えます。その際に家に帰りたいとナースコールを押して言われたりセンサー感知し起き上がり時に言われることがあります。まず入院していることを伝えたり、言葉で伝えて理解されないときは本人が落ち着くまで一緒にお話しすることもあります。その後落ち着き入眠されることもありますが眠れない時は不眠時の内服を行います。不眠時の薬とは「睡眠導入剤」と「睡眠改善薬」があります。睡眠導入剤は医師の処方が必要でベンゾジアゼピン系と言われる即効性があり寝つきを良くするハルシオンやレンドルミンや非ベンゾジアゼピン系と言われる入眠促進効果が高く翌日に持ち越すことが少ないとされているマイスリーやルネスタ、メラトニン受容体作動薬と言われる体内時計を整え自然な眠りを促すロゼレムなどがあります。またオレキシン受容体拮抗薬と言われる覚醒に関わるオレキシンの働きを抑え、自然な眠りを促すベルソムラ、デエビゴなどが該当します。睡眠改善薬は市販されており一時的な不眠に効果があります。また漢方で対応されることもあります。内服した時はふらつくため転倒の危険性がありその後の観察はとても必要になります。
用事はなくて押してみた
これも高齢者が行うことが多くナースコールではなくセンサーを使用している際も起き上がりが頻回な時に何度もセンサー対応することがあります。ナースコールを理解されていない場合も多いと言えます。何度も押される様子であれば一時的にナースコールを本人から離すこともあります。
お茶を飲ませて
お茶を飲ませてのナースコールは多くあります。起き上がれない高齢者や、術後で安静の場合介助がいるためナースコールがあり対応します。高齢者になると誤嚥をしてしまうことも多くあるためとろみをつけたお茶を楽のみやスプーンで摂取していただきます。誤嚥の状況でとろみの硬さは調整しています。
体の向きを変えて欲しい
これも術後に同じ姿勢での腰痛が出現し体位交換を希望されることがあります。その際にナースコールがあり体位交換を行います。また体位交換は褥瘡や廃用症候群の予防、循環障害の改善、呼吸機能の向上など様々な目的のために重要です。自己での寝返りができない患者さんは希望されます。褥瘡は長時間同じ体位でいることで特定の部分に圧力が集中し血流が悪くなり起こります。そのため体位交換を行い圧力を分散させて褥瘡の発生を防ぎます。廃用症候群の予防とは身体を動かさない状態が続くと筋力の低下、関節の拘縮、呼吸機能の低下などが起こります。体位交換はこれらを予防し身体機能を維持するのに役立ちます。また体位交換によって血流が促進され循環器系の機能低下を防ぎます。関節拘縮の予防や精神的な安楽にも繋げることができます。
まとめ
今回はナースコールの内容と対応方法についてお伝えしました。日中よりも夜間になることが多く、夜間は不安になるため看護師を呼ぶ傾向にもあると思います。ナースコールは命綱ともなり得るためきちんとした対応を行うことが必要です。ナースコールの連打に困ることもありますがなぜ押しているのかを考えるときちんとした対応が必要であると感じることができます。よろしければ参考にしてください。