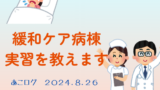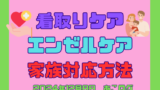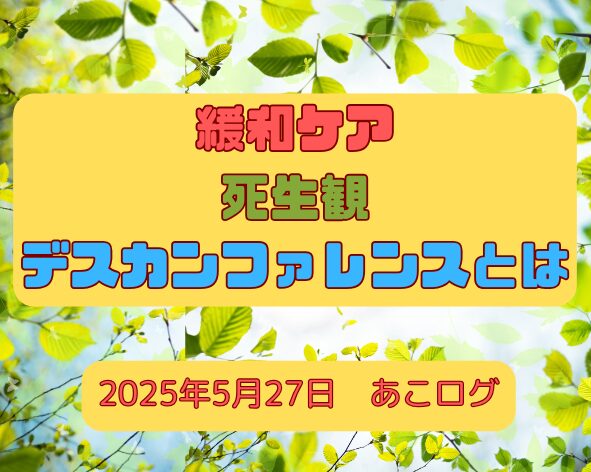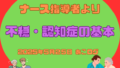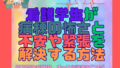ナース指導者が教える 看護師から見た緩和ケアと死生観、デスカンファレンスの意義と現状
今回は以前疼痛コントロールについての基本とケアについてお伝えしましたがそれに伴って、緩和ケアと言われる看護のケアと死生観について、緩和ケア後に行うデスカンファレンスの意義と現状についてもお伝えして共有いただければいいと思い、ブログを作成しました。よろしければ参考にしてください。
緩和ケアとは
生命を脅かす病気に直面している患者とその家族の生活の質(QOL)を向上させるための身体的、精神的、社会的な苦痛を和らげるケアのことです。終末期と言われる患者の疼痛コントロール、家族へのケアも含まれます。
緩和ケアの目的
- 苦痛の緩和:痛み、息苦しさ、吐き気、不眠などの身体的な苦痛や不安、悲しみなどの精神的な苦痛を和らげます。社会的苦痛、治療に対する苦痛、今後の人生に対する苦痛、体の変化に対する苦痛を和らげるケアを行います。
- 生活の質の向上:患者がより快適に、その人らしく生活できるようにサポートします。
- 家族の支援:家族の心の負担を軽減し、患者のケアをサポートします。
緩和ケアとホスピスケアの違い
緩和ケアとホスピスケアでじゃケアを開始する時期とチーム体制に少し違いがありますがケア内容はほとんど変わりはありません。重病を患った時に自身の病気がどういった状況なのかによって緩和ケアとホスピスケアを選択することになります。緩和ケアはがんの疼痛をコントロールしながら日常生活を送る病棟でホスピスケアも余命の近い患者さんが最期まで希望通りに生きる療養の場です。緩和ケアとホスピスケアの治療やケアはほぼ同じであり、明確な線引きはされていません。ホスピスケアは病棟だけでなく老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などでも提供されています。
緩和ケアの対象者
国内ではがん、エイズ治療を中心に発展していますが、病院によってはエイズ治療に対応できない病院もあります。
緩和ケアを受ける方法
通院、入院、自宅療養とあります。自宅では持続的な医療麻薬での疼痛コントロールができない場合もあるため疼痛が悪化する際は病院に入院されることもあります。一般的には本人とご家族の意向で療養方法を決定されます。入院していても外出されたり、外泊されたり、一時退院して経過を見る場合もあります。病状の悪化も踏まえて、医師と患者本人、ご家族の相談後に方向性が決まる場合もあります。
緩和ケア病棟入院時に確認すること
患者本人やご家族に告知の有無がされているか、緩和病棟がどういう病棟か知っているか、余命を知っているか、病名を知っているかなどを入院時にご家族に確認し、その情報をスタッフ間で情報共有してケアを行います。これらが守られることは看護師としての基本となり、一般的な個人情報保護にも通じるところとなっています。
緩和ケアのチームとは
医師・看護師・薬剤師・リハビリ・栄養士・ソーシャルワーカーなど様々な職種が協力して情報共有を行い、患者本人やご家族の意向を尊重して対応してます。定期的な病状説明やカンファレンスも行い方向性も検討されています。
余命告知とは
医師の診断のもと余命は決められますが、それは入院時にご家族には以前入院前に告知されたかの確認され、その後緩和ケア病棟で再度確認して死に対する心づもりなどを説明していきます。どのような流れで死を迎えるかも入院時にパンフレットなどを使用して医師より説明されます。緩和ケアに入院する時点で受け入れはできている方が多く、パンフレットで説明しても理解されるように感じています。また状態が急減に悪化し意識レベルの低下や血圧低下、心停止、呼吸停止での発見となることもあるため、そのことも医師より説明が行われます。
死生観について
看護師は緩和ケア病棟に入院したり、がん患者の緩和ケアに携わることで死生観についても考えることが多くあります。人間が生きること死ぬことに対する考え方、人生における死と生についてどのように考えるか、死をどのように捉えるのか、どう生きていくのかの価値観を患者本人やご家族のお話を聞くことで理解できます。それぞれの宗教や文化、個人の経験によってそれは様々であり、看護師もこれを理解していないと対応できない状況にもなります。死生観を意識することで限られた人生の終わりに備え、より豊かな人生を起こすようにトライできることは緩和ケアだけではなくこれは一般社会でも大事であると言えることだと感じています。
デスカンファレンスの意義・現状
患者が病院で死亡退院された際に医療、介護スタッフが集まり、その患者のケアを振り返り意見交換を行う場です。これは他職種で行う場合もありますし、病棟や施設のスタッフ間で行う場合もあります。目的としては終末期ケアの質の向上、心理的負担軽減、チームワークの向上などが挙げられますが今後のケアでの向上が一番の目的とされています。その中でご家族への対応や、スピリチュアルについても項目があり、ご家族への対応はどうだったか、悲観的な場面での訴えなどに対してどのように対応したか、学んだかなどを含まれます。スピリチュアルについては宗教的な観点で問題点はなかったかなどのことや死に対しての捉え方などもどのような訴えがあったか、看護師の関わりはどうだったかなども考えるようになっています。改めて患者の対応はどうだったかなどを振り返ることはとても重要なことであると考えられます。
緩和ケア病棟でのデスカンファレンス
緩和ケアでのデスカンファレンスは入院時からの病態、余命、などからどのような治療をして病態の変化があり、ご家族の受け入れはどうだったか、患者本人の状態変化や疼痛のコントロール、安楽に過ごすことができたか、死生観、スピリチュアル、チームスタッフの協力的なケアの有無などが内容として書かれています。患者自身の最期に対して最善のケアが行えたかが重要視とされています。
参考サイト:日本緩和医療学会 緩和ケア.net
最後に
今回は緩和ケア、死生観、デスカンファレンスについてブログを作りました。看護師は生死に関わることが多く、精神的にまいってしまうスタッフも現実にいます。あまりにも死にかかわりすぎて病んでしまったり、回復していく姿を見たいと職場を変える方もいます。それは人ぞれぞれであり、死に対して受け入れるケアをしたい、関わりたいという看護師もいます。患者本人やご家族の対応することはどのケアでも一緒であり、心身のケアを行うことはとても難しいと考えさせられることもあります。その振り返りとしてのカンファレンスや生死について考えることは看護師としては必要なことであると改めて感じました。よろしければ参考にしてくださいね。